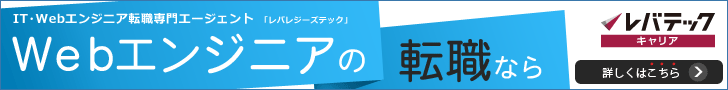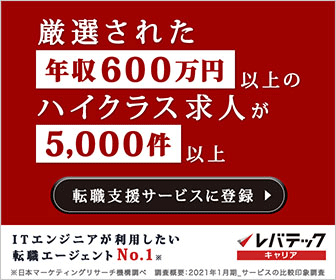「客先常駐SESは偽装請負がほとんど?」
「偽装請負というワードはよく聞くけど詳しく知らないなぁ。」
「そもそも違法なの?」
このような疑問を持っていないでしょうか?
偽装請負という言葉はSESで働いている方なら、一度は聞いたことがあるでしょう。
結論を言えば、偽装請負は違法で発覚すれば罰則の対象です。
しかし、違法にも関わらずSESでは当然のように行われているのが現状です。
「なぜ、偽装請負は行われる?」
その理由を知れば、SESはブラックと言われている理由が理解できるでしょう。
本記事では以下の内容を扱っています。
- 偽装請負とは
- 偽装請負の問題点
それぞれの内容を掘り下げて、簡単に分かり安く解説していきます。
ぜひ、参考にしていただきSESの闇を理解しましょう。
偽装請負とは?

偽装請負とは派遣と変わらない働き方にも関わらず、「準委託契約(SES)」と偽ることです。当然、違法行為として罰則の対象になります。
要するに、契約内容と実態が異なれば違法と判断されるということです。
では、なぜ企業は偽装請負を行うのでしょうか?
簡単に言えば、企業の負担を減らしたいからです。
「エンジニアは二の次三の次。」
そんな考えでしょう。
ここでは、以下の内容をご説明します。
- SES・派遣・請負の違いは?
- 偽装請負と判断されるケース
- なぜ企業は偽装請負を行うのか
SES・派遣・請負の違い
偽装請負を理解するために、SES・派遣・請負の違いを説明します。
| 契約 | SES(準委任契約) | 派遣 | 請負 |
| クライアントからの指揮命令 | なし | あり | なし |
| 納品・成果物の完成責任 | なし | なし | あり |
| 成果の判断基準 | 稼働時間 | 稼働時間 | 納品物 |
SESと派遣の違い
SESと派遣の違いの一つは、法律で定められているかどうかです。
派遣は法律で定められており(派遣法)、対してSESは業務委託(準委任契約)として法律では明確な定めがありません。
要するに、SESの契約にも関わらず常駐先企業で派遣契約の形態をとっていれば、法律違反で罰則を受けます。
よく問題になるのは、指揮命令系統についてです。
SESはクライアントがエンジニアに対して作業内容を伝えるのみで、指揮命令ができません。対して、派遣はエンジニアがクライアント企業の命令で業務を進めます。
しかし、実際のところはクライアントから指示を受けて派遣のような働き方をしている現場がほとんどです。
請負契約について
次に、請負契約について説明します。
エンジニアがシステム開発を行う時に結ぶ契約は、「準委任契約」か「請負契約」がほとんどです。
請負は仕事を完成させる責任があり、納品物で報酬が支払われます。
準委任契約は、仕事の遂行を目的とした契約です。
適切に業務を行えていれば、成果物の納品義務はありません。
言い換えれば、出勤さえしていれば成果物を完成させなくも良いということです。
もちろん、社会人としてそんなことはNGですので、法的な罰則を受けなくても信用を大きく下げるでしょう。
繰り返しますが、契約内容と実態が異なれば違法と判断される可能性が高いです。
偽装請負と判断されたり、疑われるたりするケース
指揮命令者が常駐先(クライアント) :
指揮命令者がSES契約の場合と異なる場合は、偽装派遣と判断されます。
繰り返しますが、SESはクライアント(客先)から指揮命令ができません。
対して、派遣契約はクライアントに指揮命令権があります。
エンジニアが客先から指揮命令を受けた場合、派遣契約と同じ形態なので偽装請負と判断されます。
単独配属のケース :
一人で常駐先に配属されている場合、偽装請負と判断される可能性が高いです。
クライアントからの直接指示や勤怠管理を受けるのが、必然だからです。
単純労働の場合(疑われる) :
単純労働の場合は、偽装請負と判定されると言うよりも疑われる可能性が高いです。
通常、雑用的な仕事はスキルが低い人が配属されます。
単純労働の場合、専門性がないのでクライアントから直接指示をした方が手っ取り早いです。
クライアントから作業内容の説明を受けた後、自社だけで専門技術を用い業務を行うとは考えづらいです。
「現場から、直接の指示を受けたのでは?」と疑われる場合もあるでしょう。
なぜ会社は偽装請負を行うのか?
労働者派遣には労働基準法が適用されるので、労働者の権利を守ることでき企業側は厳しく規制されます。その規制を逃れるために企業は偽装請負を行います。
偽装請負が行われると、請負で契約するので労働者が保護されなくなります。
労働基準法が適用されないことで、以下の可能性が出てきます。
- 残業代が請求できなくなる
- 労災にあっても保険の支給がない
請負は成果物に対して報酬が支払われます。
したがって、客先はいくら残業させても残業代を払う必要がありません。
客先にとってみたら、非常に有利な契約です。
続いて、労災が発生した場合ですが、派遣先(クライアント)と派遣元(SES企業)の両方が労働基準監督署に対して報告しなければいけません。(報告をしないと法的な罰則を受ける)
会社にとって厄介なのは、報告の段階で偽装請負がバレてしまうことです。
業務中は「誰が指揮をとって、どのように指示を出していたか」などを正確に報告する必要があります。
仮に、偽装請負を行っていたら確実にその事実が分かり、企業の信用は低下するでしょう。
以上のことから企業は偽装請負を行い、さまざまなリスクから逃れるようとしています。
エンジニアの生活よりも自社の利益を優先しているのが、丸分かりですよね。
偽装請負の問題とは?

偽装請負を行うと、企業は罰則を受け企業の信用が低下します。
さらに、その企業で勤務したエンジニアの将来にまで影響が出るでしょう。
ここでは、「どのような罰則を受けるか」、「エンジニアの将来にどのような影響が出るか」を説明します。
企業は罰則を受ける
労働者派遣法による罰則 :
許可を得ないで一般労働者派遣事業を行った場合の罰則です。
「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が課されます。
行政処分 :
偽装請負を行うと懲罰以外にも、「是正勧告」や「行政指導」などの行政処分を受ける可能性があります。さらには、「事業停止命令」や「社名が公表される」される可能性もあるので企業は大きく信用を失います。
エンジニアの将来にも影響が出る可能性がある
偽装請負は、企業の信用を下げるだけではありません。
違法を行った企業で働いていたとして、社員の信用まで下げます。
例えば、エンジニアがSESから他の企業に転職をするケースです。
採用では、前職の企業名や雇用形態だけで判断する企業もあります。
前職がSESというだけで採用をためらう企業が多い中、偽装請負で罰則を受けた企業での勤務経験は確実にマイナスです。
公に社名を公表された場合はさらに市場価値は下がり、今後に影響を及ぼすでしょう。

客先常駐SESの偽装請負は完全に社員を軽視している
偽装請負は完全にエンジニアを軽視していると言えるでしょう。
企業はリスクを避けるために、手段を選んでいないからです。
違法であろうが、利益のためなら関係ないのでしょうか。
そもそも、SESは人材が命のはず。
企業が最も大切にすべきなのはエンジニアです。
それどころか、社員の生活や保証は二の次。
「自社さえ有利な契約が出来ればそれで良い。」
言葉は悪いですが、エンジニアを商売道具としか見ていないのと同じです。
まさに、SESの闇でしょう。